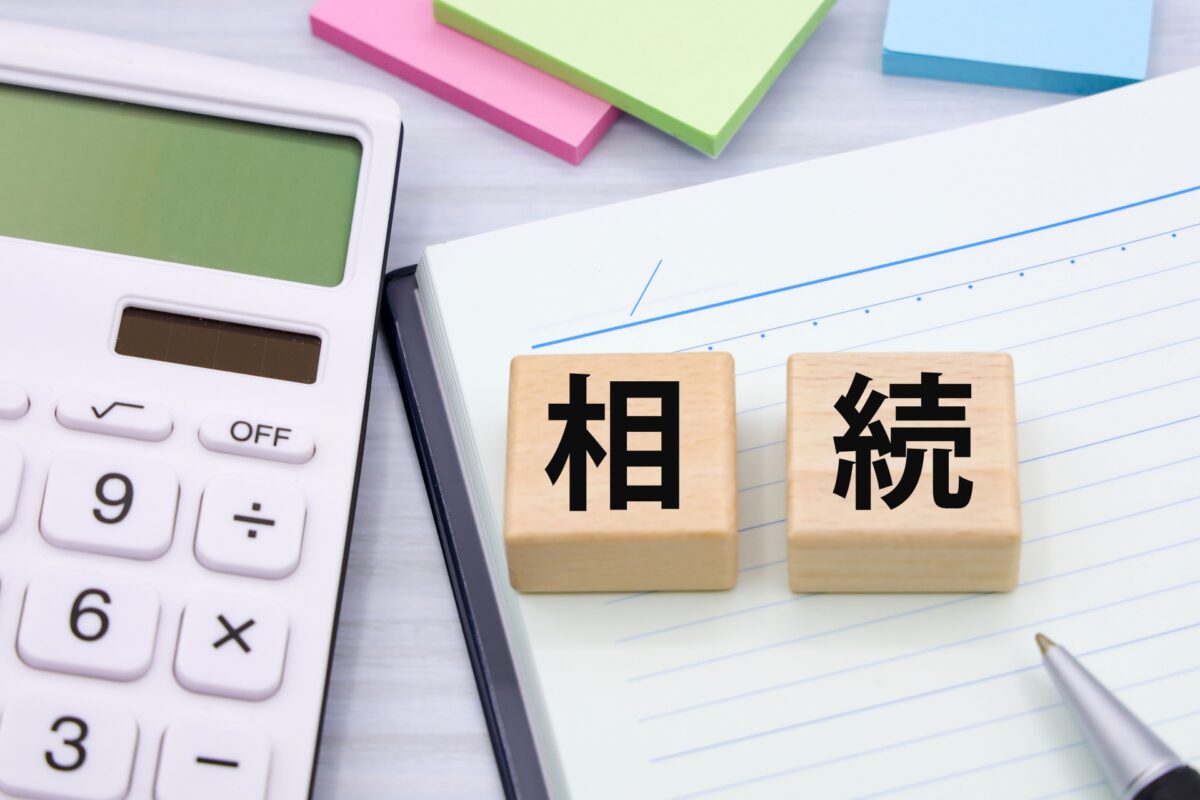相続財産に未登記の建物が含まれている場合、どのように扱うべきか、
どう登記を進めるべきか分からないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続と未登記建物に関連する手続きや必要書類について解説します。
相続の際に、遺産に未登記建物が含まれていると、所有者が不明確なままとなり、
相続手続きが複雑になることがあります。したがって、まずその建物の所有権を明確にし、登記を行う必要があります。
ではそこで、未登記建物を誰を所有者として登記するのかという点があります。
実際は、相続開始後においては亡父、亡祖父のものであったりするわけですが(それ以外のケースもあり)、実務上は、それを相続人の名で登記することが多いかと思います。
ただし、ケースによっては被相続人の名で登記したりすることも実務上は可能です。
その説明は今回は割愛いたします。
では、相続人の名で登記する場合には、どのような書類が必要になるか。
それは、「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は、相続人全員が集まって、遺産をどのように分けるか話し合い、その結果を文書としてまとめたものです。特に未登記建物が遺産に含まれている場合、遺産分割協議書にその建物の所有権をどのように分けるか、誰が所有するのかを明確に記載する必要があります。
例えば、未登記建物が実家であり、相続人のうち一人がその建物を引き継ぐことになった場合、その相続人が所有権を主張するために、遺産分割協議書にその旨を記載することが重要です。この協議書があれば、後に登記手続きや税務署等への申告もスムーズに進みます。ただし、相続人が多い場合や数次相続などの場合、そもそも未登記建物が多すぎて特定しにくい場合などは遺産分割協議書も複雑になってきますので、その点については専門家に相談することを強くお勧めいたします。
いずれにしても、相続した未登記建物を売却する場合や、第三者に賃貸する場合、登記がされていないと法律的に所有権を証明することができず、さまざまな問題が生じることがあります。したがって、未登記建物を相続した場合は、早めに登記を行うことを強くお勧めします。