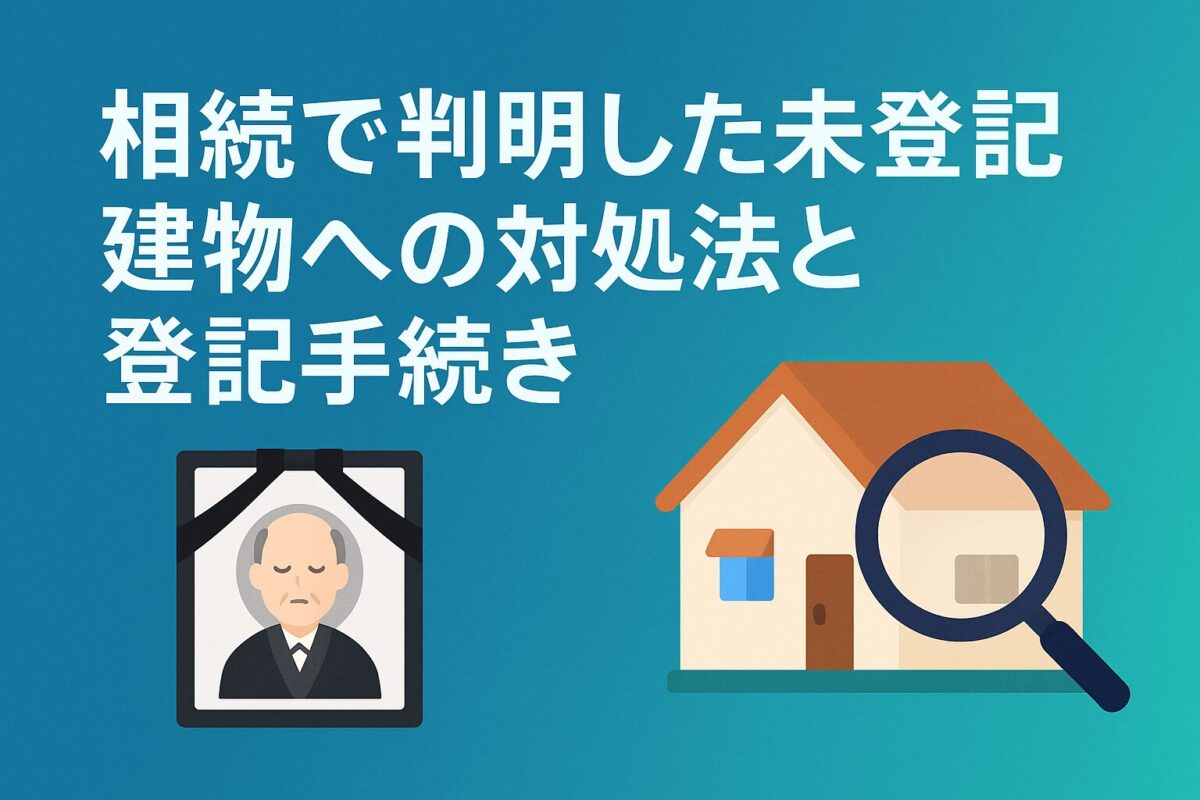相続で判明した未登記建物への対処法と登記手続き
相続手続きを進める際、「相続財産に建物があるのに登記簿に記録がない=未登記建物」というケースが少なくありません。祖父母の代から住んでいた家が実は登記されていなかった…というのは珍しくないのです。放置すると売却・分割・融資ができず、遺産分割協議も前に進まないリスクがあります。
未登記建物が相続に与える影響
- 遺産分割協議が進まない:登記簿がないと誰の名義にもできず、協議書の作成に支障。
- 相続登記ができない:所有権移転登記は「表題登記」が前提。表題登記がなければ相続登記そのものができない。
- 売却ができない:相続後すぐに売りたい場合でも、表題登記を先に行わなければ売買契約は実現しない。
- 相続税評価が不明確:登記簿に記載がなくても課税はされるが、評価資料が不足し税務申告で不利になる可能性。
相続で未登記建物が判明したときの流れ
- 現況調査:建物の所在地・種類・構造・床面積を実測し、登記可能な状態か確認。
- 資料収集:建築確認済証、固定資産税課税明細書、古い売買契約書などを確認。
- 建物表題登記を申請:土地家屋調査士が「建物図面」「各階平面図」を作成し、法務局へ申請。
- 表題登記完了後:司法書士が「相続登記(所有権移転登記)」を申請。これで正式に相続人名義に。
注意点
- 期限:建物表題登記は「所有権取得日から1か月以内」が原則(不動産登記法第47条)。相続の場合も、早めの手続きが推奨されます。
- 書類不足:古い建物では建築確認済証がないことも。その場合は固定資産税の資料や実測図面で代替可能。
- 共有相続:相続人が複数いる場合、遺産分割協議が必要になる場合があります。
まとめ(要点)
- 未登記建物は相続登記の前提条件。放置すると遺産分割や売却ができない。
- まず表題登記 → 相続登記の順序で進める。
- 書類がなくても、固定資産税資料や実測で対応できる。
- 専門家(土地家屋調査士+司法書士)を活用することでスムーズに完了。
ご相談受付:「相続した家が未登記かもしれない」「登記がなく売却が進まない」といったケースも対応可能です。お気軽にご相談ください。